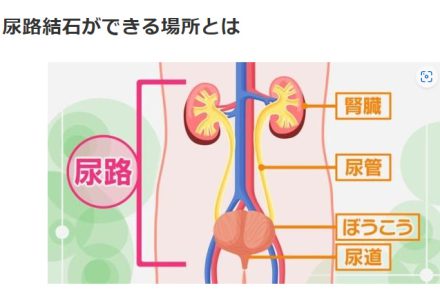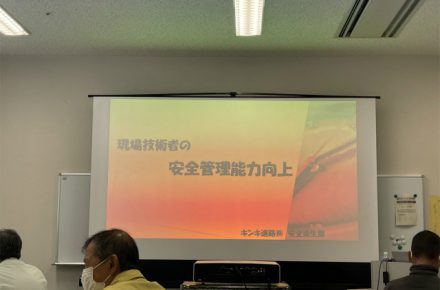舞鶴市 城屋・・・・とは
みなさんこんにちは倉橋です。
本日は・・・
舞鶴市 城屋…とは・・・
毎年8月14日、京都府舞鶴市城屋で『城屋の揚松明』(じょうやのあげたいまつ)が奉納されます。雨引神社の境内で、高さ5丈3尺(16m)の大松明に、地元の青年たちが火の付いた小松明を投げ上げて点火する伝統民俗行事。森脇宗坡の娘が大蛇に飲み込まれ、その大蛇を退治したという伝説による不思議な祭礼です。
弘治2年(1556年)、丹後国守護・一色義幸(いっしきよしゆき)の治世、城屋は家臣で女布城(舞鶴市女布にあったという戦国時代の山城)城主の森脇宗坡(もりわきそうは)が治めていましたた。
森脇宗坡の娘は隣村に嫁ぎましたが、里帰りのため女布城に向かい、山中の日浦ヶ谷を歩いていた際、大蛇に飲み込まれてしまいます。
怒った森脇宗坡は、娘の敵(かたき)を討つために、高野川上流部にある蛇ヶ池へと向かい、炎を吐く大蛇を、死闘の末に退治。
頭部を雨引神社、胴体を中之森神社(舞鶴市野村寺)、尾は尾森神社(舞鶴市高野由里)に祀ったと伝えられています。
深夜、高野川の清流で身を清めた氏子たちは、点火した小松明を大蛇の長さと同じ5丈3尺(16m)もの大松明に向かって投げ、大松明を燃え上がらせますが、松明が夜空を焦がす様子は、大蛇が火を吐き出す姿とも、大蛇の断末魔の姿とも伝えられています。
もともと雨引神社は水分神(みくまりのかみ=水の分配を司る神)が祭神で、雨乞いの神様ですが、大蛇を合祀(ごうし)した後、「蛇神様」となった雨引神社に揚松明を奉納するようになったもの。

雨引神社の境内

雨引神社の境内

無形民俗文化財 城屋の揚松明 神秘的だ・・・・